温かいものは、温かいまま食べたい。
だから、スープジャーを購入したんだと思います。
しかし、食べるころになったら実際は冷めていた。
と言う経験はありませんか?
原因は、スープジャーをきちんと使いこなせていないからかもしれません。
ちゃんと使い方を守らないと冷たいどころか、衛生的にも良くないかも・・・
このブログを読んで、もう一度おさらいしてみましょう。
- スープジャーの使い方
- お昼まで温かさを保つ方法
- 清潔を保つ洗い方
スープジャーの基本的な使い方
①スープジャーは、熱湯で消毒&予熱
スープジャーに熱湯を入れて、フタをせずに5分ほど置いておきましょう。
こうすることで、スープジャーの中を消毒をすると同時に、予熱をします。
スープジャーの中を予熱することにより、保温力が高まり、お昼まで温かさをキープできます。
②お湯を捨てたらすぐに料理を入れる
せっかく予熱をしても、冷めてから料理を入れてしまったら、予熱した意味がありません。
消毒・予熱に使ったお湯を捨てたらすぐに、料理または材料を入れましょう。
③生の食材は入れない
生ものは、スープジャーの中の温度も下がりますし、衛生的にも良くありません。
肉・野菜などは必ず、火を通してから入れるようにしましょう。
ハムなどの加工食品や葉物野菜などすぐに火が通ったり、そのまま食べられるものは、予熱の時に一緒にスープジャーの中に入れて温める程度で大丈夫です。
④容量を守る
スープジャーの容量を守らないと冷める原因になります。
保温調理もできなくなりますので、内側に線がある場合は、内側の線まで。ない場合は、口の下1cmぐらいまでお湯や料理を入れましょう。
おすすめレシピ
私が良く作っているリゾットのレシピです。
簡単で、10分以内にできちゃいます。
ちなみに私が使っているスープジャーは、サーモスの真空遮断スープジャー380ml。
ちょっと部品が多く洗いにくいのが難点ですが、お昼までおいしい温度を保ってくれます。
↑こちらの旧式です。![]()
なんちゃってリゾットの作り方
材料
・もち麦・・・大さじ2杯
・ウインナー・・・1本
・お好みの野菜・・・適量
(たまねぎ、にんじん、じゃがいも を主に使っています)
・お好みのスープの素・・・1袋
(ポタージュ系がおすすめです)
・塩コショウ・・・適量
作り方
4時間後ぐらいが食べごろです!
スープの素が、大体160mlのお湯で溶かすようになっているのですが、嵩を増すために野菜を多めに入れています。
朝、包丁を握るのが嫌な場合は、夜に切っておいて朝電子レンジにかければOK。
お昼には、もち麦がスープを吸って、リゾットのようになって美味しいです!
温かさを保つ為に
6時間後は〇度と保温効力を示してはいますが、これは室温20度±2度に置いた時の温度です。
季節や場所によっては、温度を保つのが難しいことも・・・
そうならないためには、2つの方法があります。
タオルで包む
スープジャーに直に冷気があたらないようにタオルで包むと温かさをキープできます。
家にあるものなので、お金はかかりませんが、見た目はあまり良くないですね。
保温・保冷バッグを使う
夏場に大活躍する保温・保冷バッグ。
周りの温度を遮断してくれるので、スープジャー内の温かさもキープできます。
専用のバッグなら見た目もスマートです。
心配ならW使い
タオルで包み、保温・保冷バッグに入れれば、単体で使うよりも温かさはキープしやすくなります。
タオルや保温・保冷バッグを使っても絶対冷めない!と言うわけではないので、ご理解ください。
スープジャーの洗い方
使っていくうちにニオイや汚れが目立ってくるのがストレスですよね。
解消するためには、どのようにすれば良いのでしょうか?
基本の洗い方
全てのパッキンや部品をばらし、洗剤をつけた柔らかいスポンジで優しく洗ってください。
スポンジが入らないパッキンの溝は、指で開きつつ指の腹で洗いましょう。
スポンジのかたい面は使わないようにしましょう。
ニオイが気になったら
どうしてもニオイがつきやすいパッキンは、40度ぐらいのぬるま湯に食器用洗剤をちょっと多めに入れて溶かします。
そこにパッキンや内蓋を入れて30分ほどつけるとニオイが取れます。
本体もぬるま湯と食器用洗剤を入れて、こちらも30分つけおきしましょう。
つけおきは、内側のみにして外側はつけおきしないようにしてください。
頑固なニオイには
それでも取れない場合は、ステンレスボトル用の酸素系漂白剤を40度ほどのぬるま湯に所定の量を溶かして30分つけてください。
 まとめ
まとめ
- 保温応力は、正しい使い方をしないと意味がない
- 寒い時は、タオルと保温・保冷バッグの合わせ技を使う
- 丁寧なメンテナンスで、ニオイは取れる
スープジャーでの保温調理は、食べるまでどうなっているかわからないのが魅力的です。
どんな味になるのかな?ってワクワクします。
スープの素を変えたり、具を変えたり、バリエーションは無限大なので、マンネリ化も防げますね。
スープジャーの選び方は、こちらをご覧ください。
本ページはプロモーションが含まれています。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
よかったらクリックをお願いします。




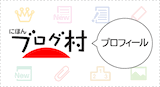
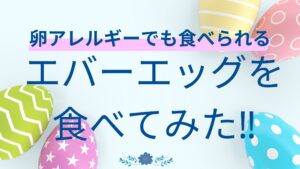


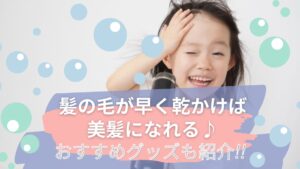

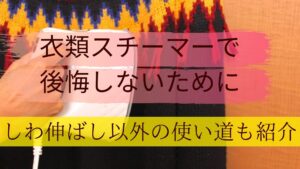


コメント